今回はユーザー企業の目線について!

ユーザー企業とは、消費者に対して事業を展開している会社を指します。
代表的なのは、自動車や家電製品など消費者向けの製品を販売してるメーカーさんですね。
ITベンダーの人たちは、こういったユーザー企業に提案や商談へ行く機会が非常に多いと思います。
そんなとき、ユーザー企業はあなたにどんな事を期待していて、どんな目線で見ているのでしょう?

相手の目線を知る事は、商談をスムーズに進める潤滑油となりますので知っておきましょう!
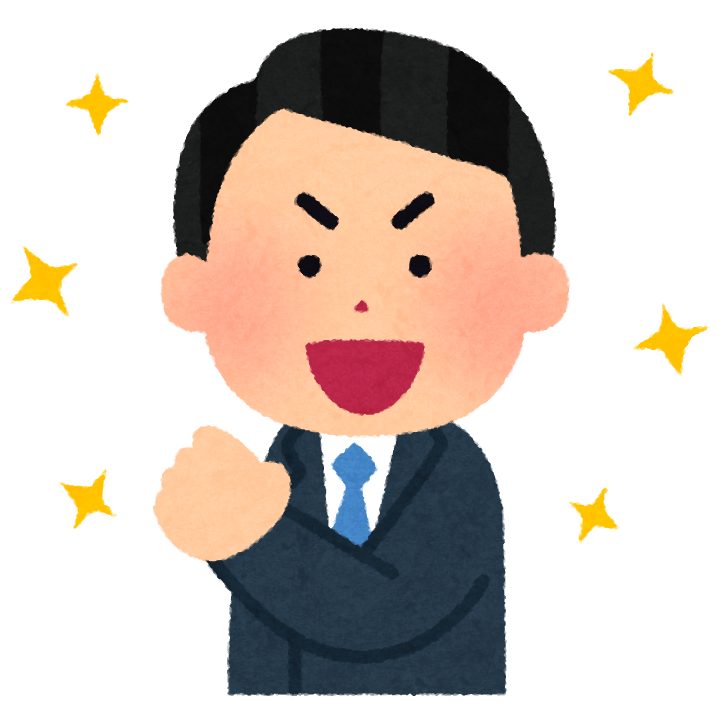
システムの投資は減らしたいが本音?
会社があんまり儲かってないと、当然経費削減を考えるのは当然です。
そんなとき対象になりやすいのが「システム」
DXだ何だとマスコミに騒がれてる今でも、システムは仕事を支援するための手段で、ビジネスの創造はできない。

こんな意識を、心のどこかで持ってる人は多数いるので、システムへ投資する優先度ってどうしても下げられやすいんです。
このように、システムへの投資に消極的になっている企業を、うまくコミュニケーションを取り誘導しなければなりません。
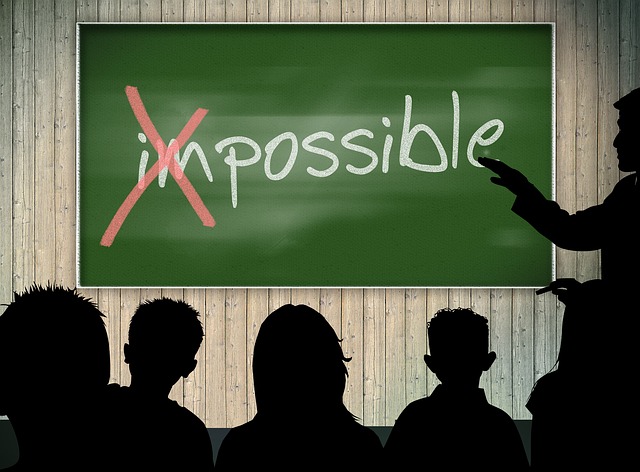
提案してるんだけどなぁ・・
解ります!

しかし提案してるつもりでも、実は相手にされていないケースが2パターンほどあります!
ただの御用聞きになってしまっている
提案をする人がただの御用聞きだと、実は信頼されてないケースが多かったりします。
例えば、相手から提案の依頼が来たときだけ提案してるとか、来た質問をそのまま回答するだけ・・などです。
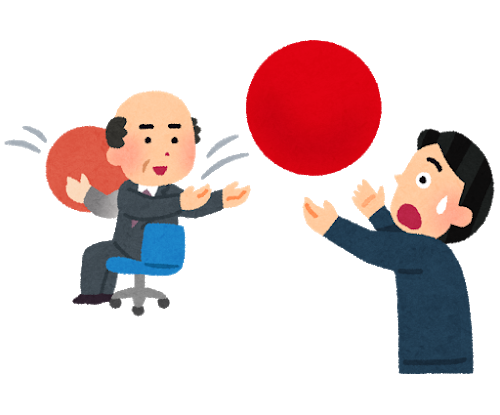
対応がこれだけでは、本気で相手にはしてもらえません、もしかしたら、相見積もりの材料として使われてるだけかも?
大事なのは、出来る・出来ないを回答をするのではなく、あなたの会社もしくはあなたが思う「意見」をユーザー企業に確実に伝える事。

ユーザー企業がITベンダーに「丸投げ」をして、発注後ITベンダーが自分なりのやり方で納品すればそれで良かった時代もありました。
しかしこの「丸投げ」が原因で、ユーザーの意思がITベンダーに伝わらず、品質の認識違いによるトラブルが多発しました。
今でもこういうケースは多く、ユーザー企業もこの点は常に警戒しているので、信頼関係を築く事がすごく重要なんです!
こういう背景もあるため、御用聞きをするだけでは、なかなか信頼されにくいんです。

システムを中心に話してしまっている
もう1つの理由は、提案内容が「システム」の話が中心になってしまってる事です。
いくら最先端の技術や仕組の話をしても、業務と結びついてなければユーザー企業には響きません。

ユーザー企業を理解する
ユーザー企業が求めてるのは「業務改善の提案」や「稟議を通すための材料」や「ビジネスモデル」です。
例えどんなに素晴らしい最新の技術を使っていたとしても、使いこなせないと何の役にも立ちません。
システムと業務をリンクさせて何ができるか?メリット・デメリットは?何が解決するか?
この辺りを具体的にどう伝えるかに重きを置いて改善活動をするのが大事なポイントです!
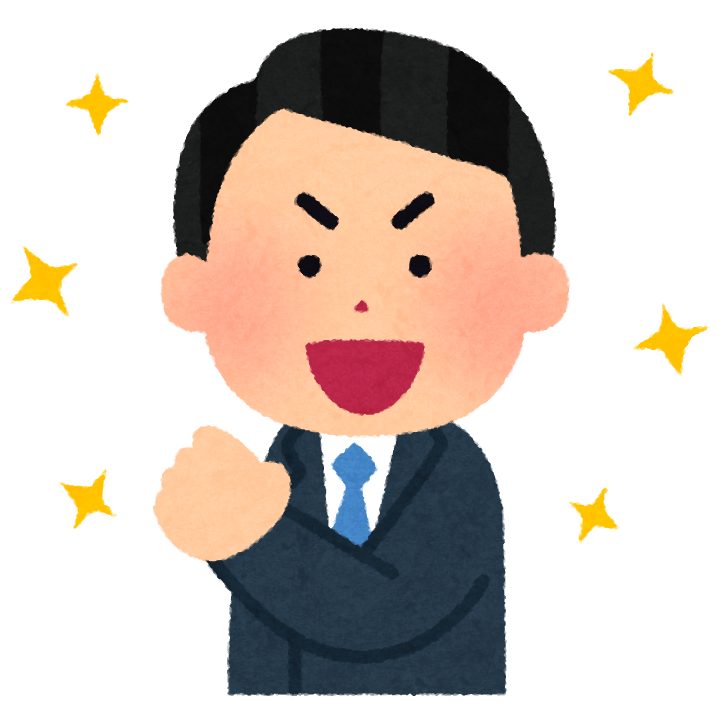
業界の知見
このように、最近のユーザー企業は「技術力」や「開発力」ではなく、業務に関わる「業界の知見」をITベンダーに期待しています。
業界の知見は、大きく3つのレベルが存在します。
- レベル1 – 指導する
- レベル2 – 仕事の会話をする
- レベル3 – ヒアリング

レベル1-指導する
このレベルはユーザー企業の業界をとりまく動向や習慣、競合他社との差を的確に診断して「業務はこうあるべき」だと指導する知見です。
ただこの方法は「業界のあるべき姿はこうだ!」と決め打ちをしてるので、相手の意見を聞かず、ずるく取り繕ったり、意固地になって、押し付けが発生したりします。
要は、決め打ちによる思い込みで、相手の意見に耳を貸すのを忘れがちになりやすいため、失敗しやすいって事です。

難しい問題ですが、レベル1については、診断士や業務コンサルに任すべきなのかもしれません。
レベル2-仕事の会話をする
レベル2はユーザ企業の問題を把握して整理する、そして過去の事例をもとにユーザー企業とディスカッションして、改善点をみつけるというやり方。
ユーザー企業は他社がどうやってやっているか?をすごく気にする傾向があります。
こんなときにITベンダーが他社の事例などの話をすると、ユーザー企業は興味を持ってくれます。

レベル1との違いは意見を押し付けないという事。
あくまで他社事例はヒントとして、気付きを与えて一緒になって改善策を考えるやり方です。
このレベル2こそがITベンダーに求められてる「業界の知見」だと言われています。
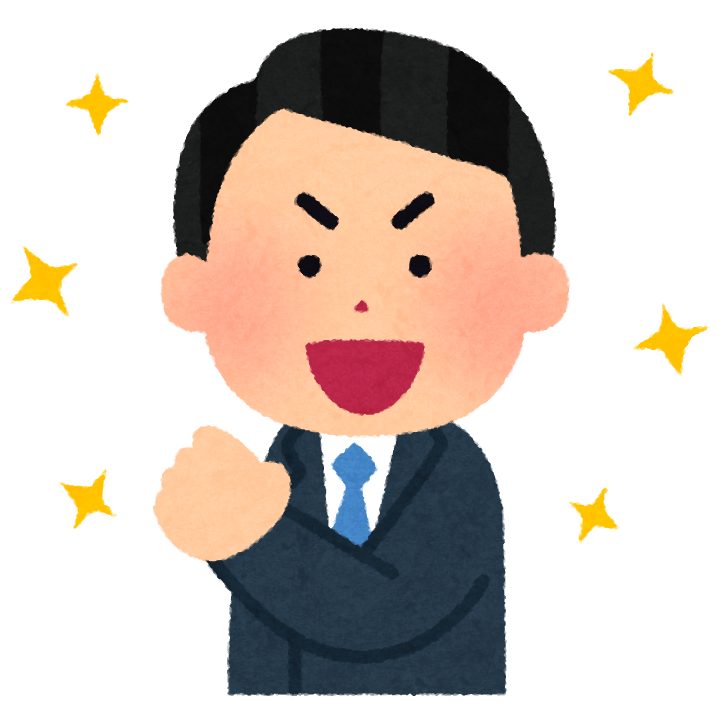
レベル3 – ヒアリングをする
あらかじめ、聞いておくヒアリング内容を用意しておいて、ユーザー企業にどのような業務をやっているか聞く方法です。
聞くだけで終わってしまう場合もあるのですが、ヒアリングをして問題の整理を支援する事で、以下のきっかけを作れます。
- 業務の話をしてもらう
- ユーザー企業が問題に気付く
- 企業が課題解決策に気付く

これがきっかけでユーザー企業が問題解決に本気になり、商談が進む場合もあります。
自分事として捉えてもらうのが大事
ユーザー企業がITベンダーに求めている「業界の知見」とは「あるべき姿を語ってくれるか」とか「指導をしてくれる」ではありません。
教科書通り型にはまったものを提案しても、それはユーザー企業自らが試行錯誤して生み出したものではありません。
こうなると、ユーザー企業は自分事として捉えませんので、結果実行を伴わない「絵に描いた餅」で終わるのです。
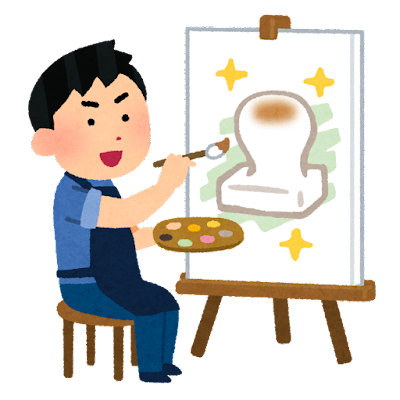
つまりユーザー企業がITベンダーに対して求める「業界の知見」とは・・
ITベンダーが他社 (色々な会社)で積み上げてきた知見です!
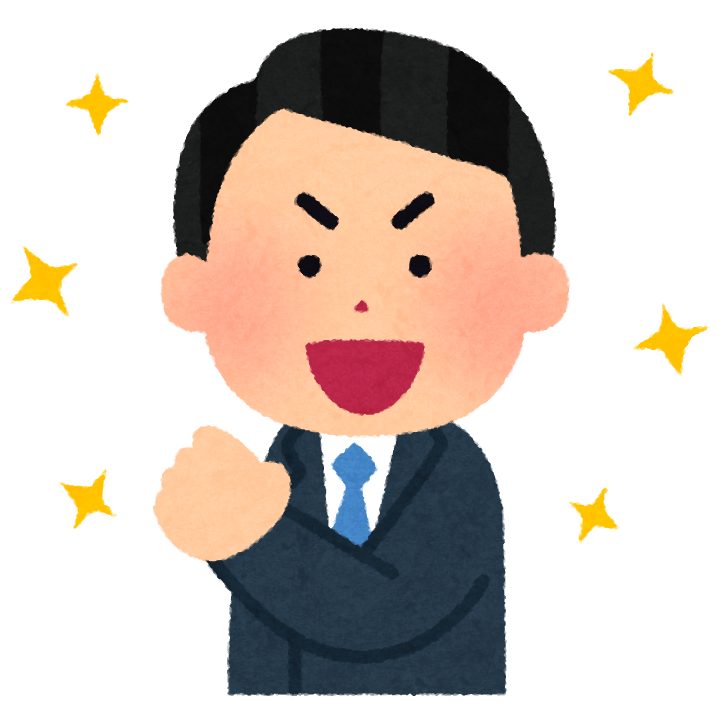
ユーザー企業に対して、この知見をもとに会話をして、課題解決を一緒に進める事。これこそが・・
ソリューションと呼ばれる提案方法なんです!

最後に
今回は「ITベンダーが他社で積み上げてきた知見」こそが武器となり、ソリューションになるというお話をさせていただきました。
でも、残念ながら多くの会社が「他社で知りえた知識」を管理しきれてません。
原因は、経験から積み上げてきた事例を、会社としての情報ではなく、個人の情報に留めてしまっているから。
これは単純に個人の事例を具体化して、ナレッジベースとして残していけばいいだけの話です。
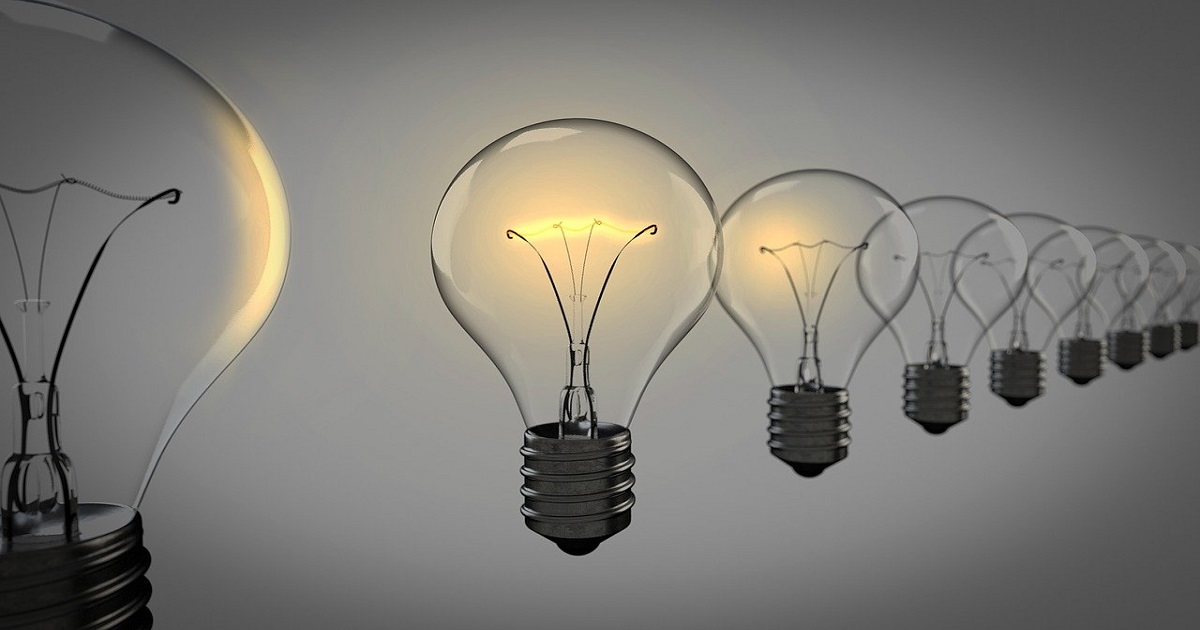
でも、実際やってみても、習慣にならず、結局誰も情報を残さなかったり、残されていても、情報が具体的ではないパターンにおちいるんです。
ナレッジを残していく事って、優先順位を低く設定されがちだし、効果も見えずらいので評価がされずらいんです。
だからどうしても習慣になりずらい傾向があります。
しかし、企業の武器となる「コア・コンピタシー」とは、こういう事例を積み上げて初めて生まれると思うんです。
※コア・コンピタシー ・ 競合他社を圧倒する能力

競合との熾烈な戦いを勝ち進んでいくには、ナレッジ管理を本気で取り組むべきです!
だからこそ私は声を大にして言いたい!
ナレッジ管理を甘くみるんじゃねぇぇぇぇぇ!

以上です!
noteで「よっしーTECH」の下書き版も公開中です! こちらもよろしくお願いします!



